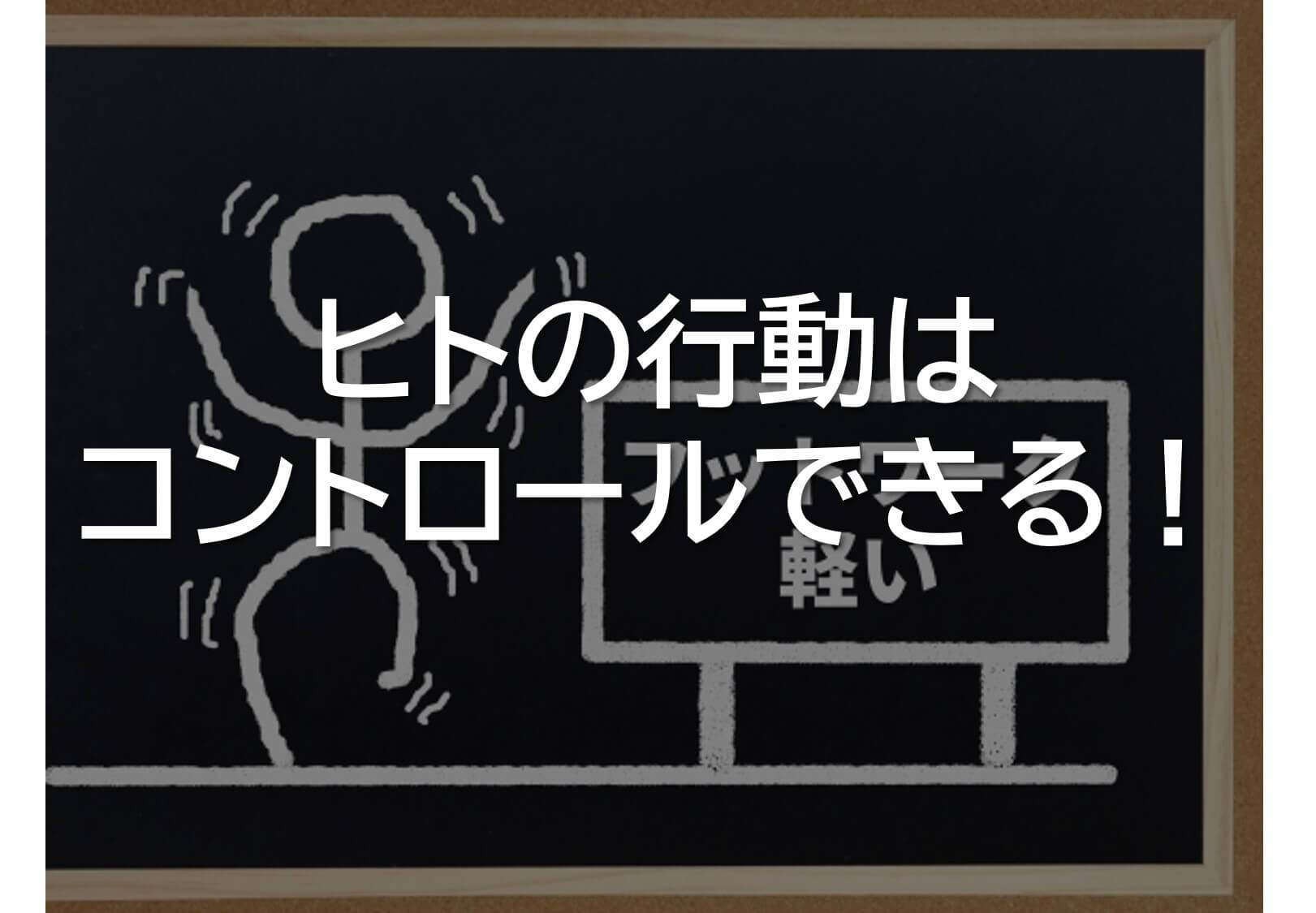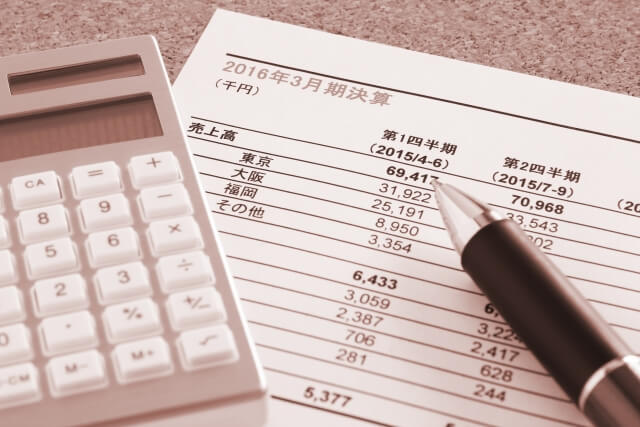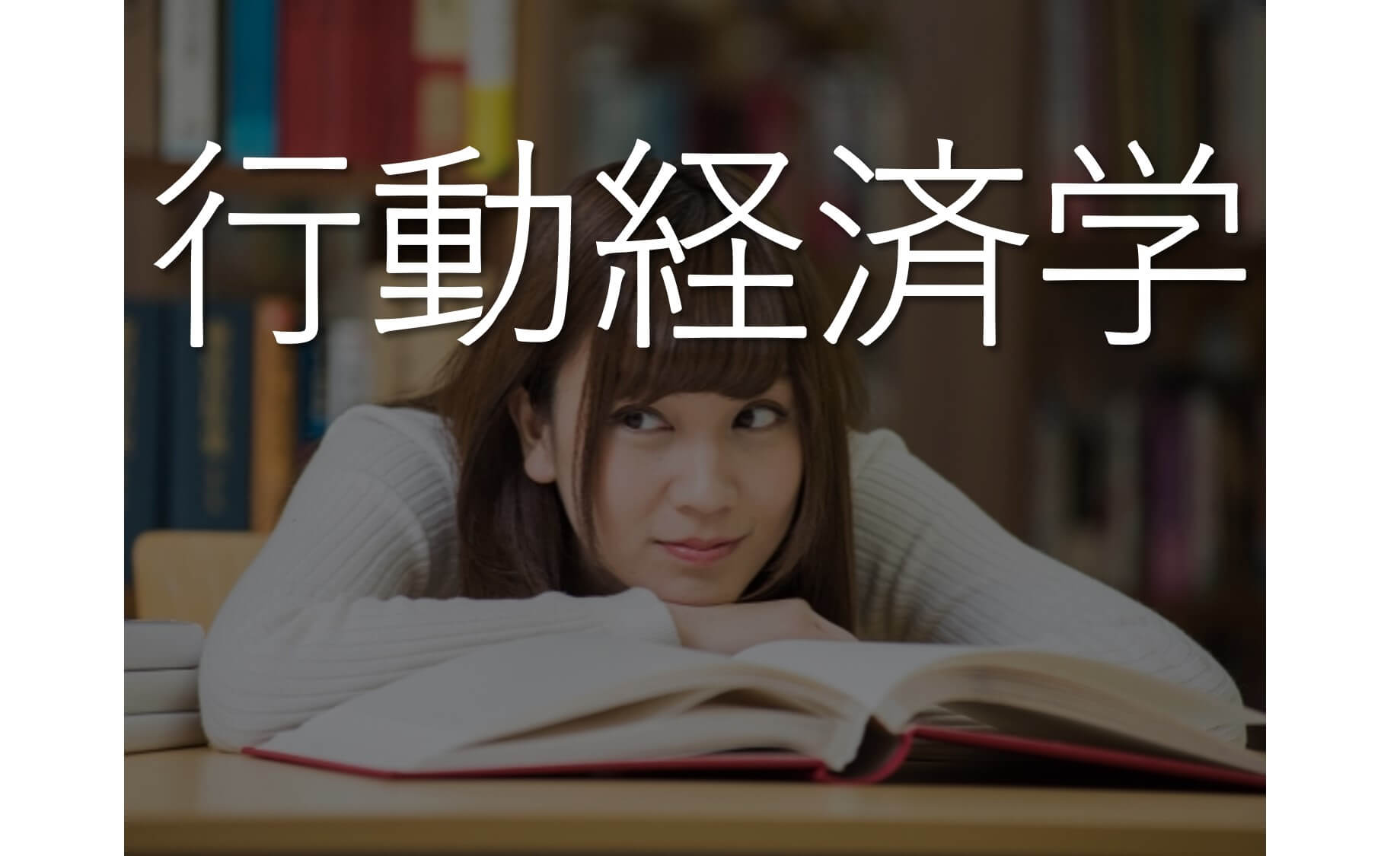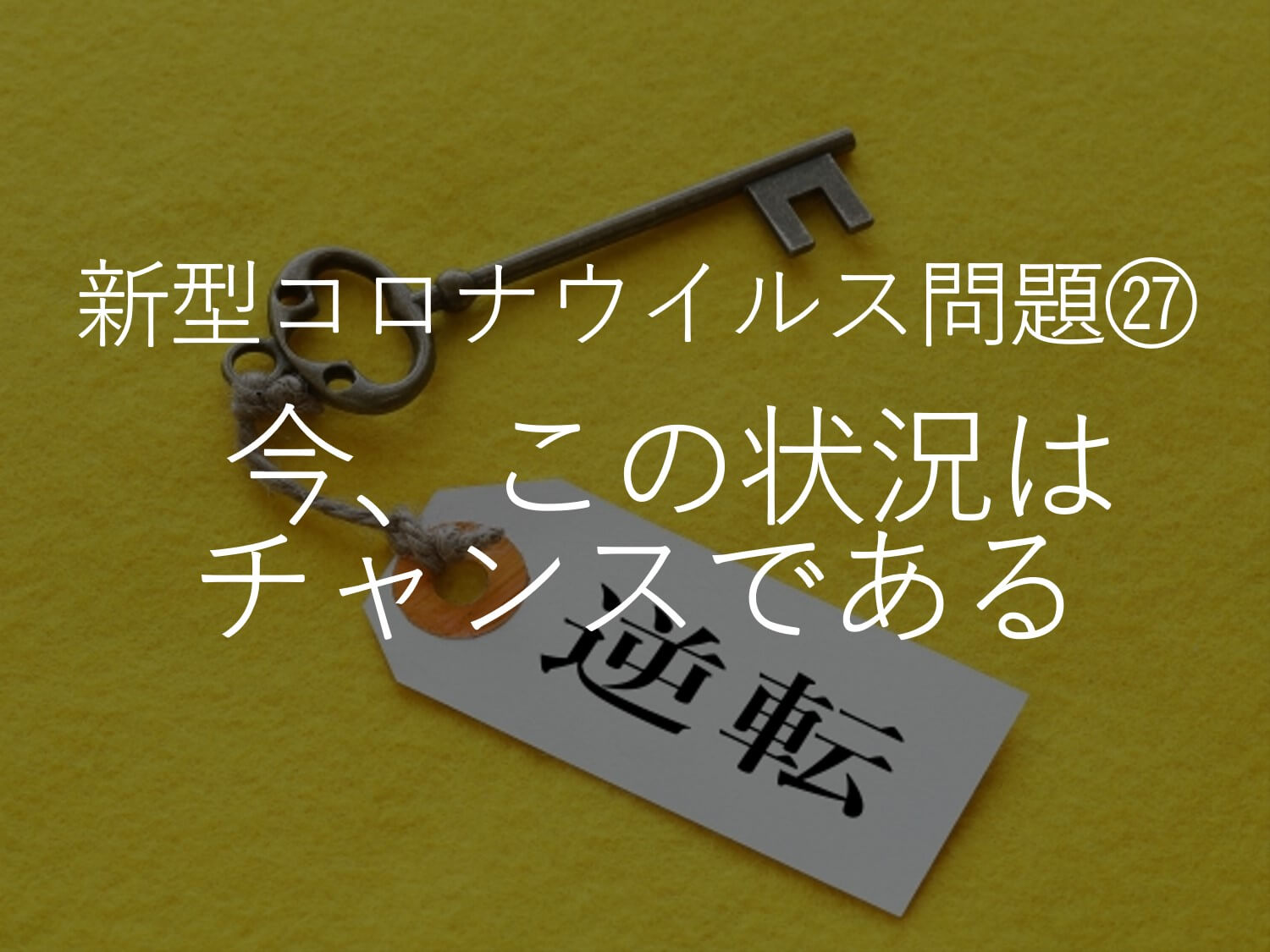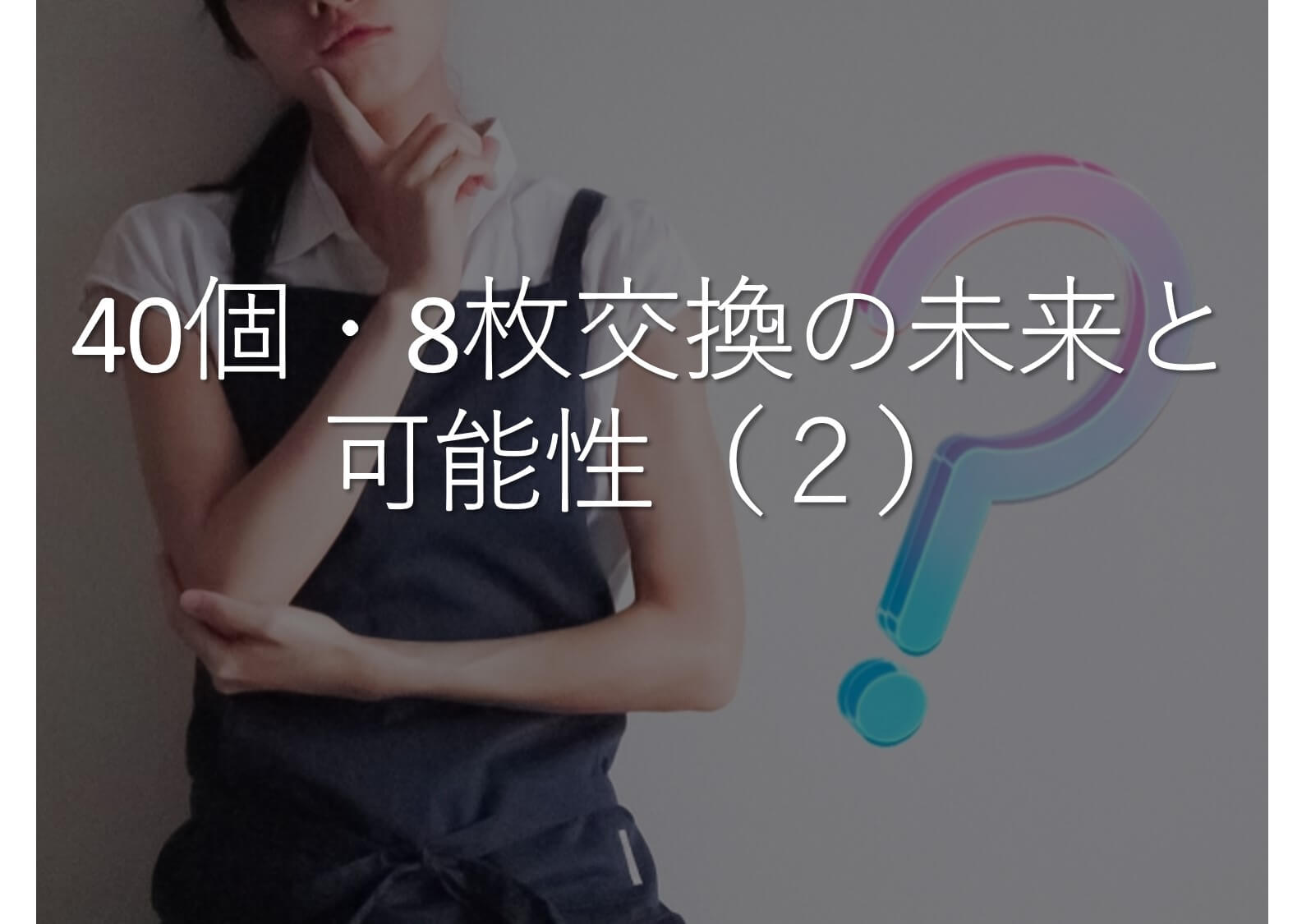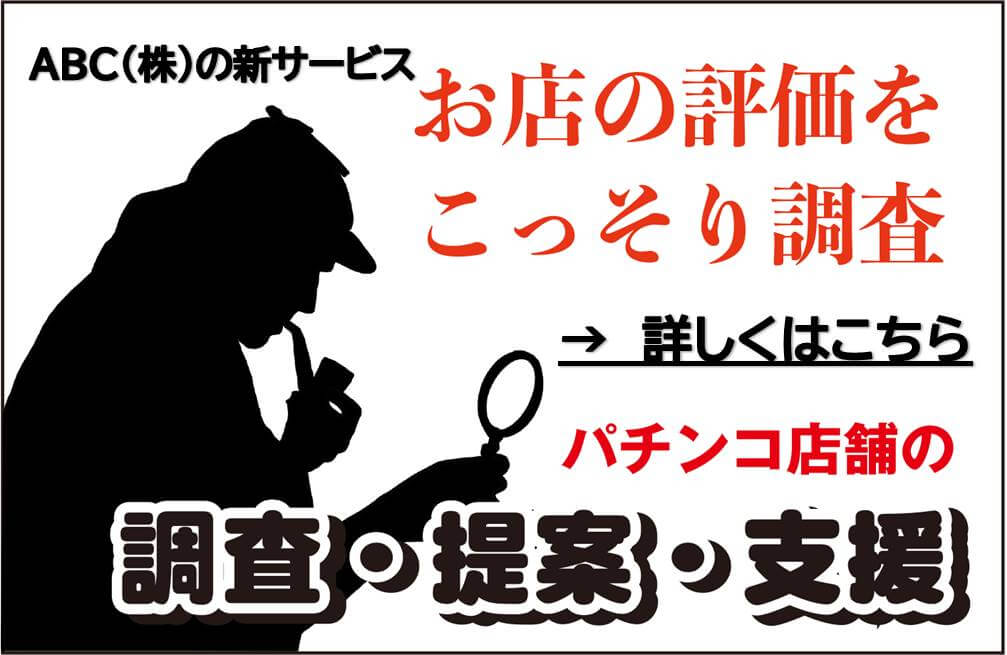【問い】
コインを投げてオモテが出たら1万円プレゼントというゲームがあります。参加料は2千円。ただしウラが出たら参加料の2千円は没収となります。なお、参加はするがコインは投げないという選択もあり、こちらの場合は3千円分のお食事券(全国で使用できる)がもらえます。
さて、あなたは参加しますか?
A.参加しない
B.参加してコインを投げる
C.参加するが、コインは投げない
どうでしょう?
この質問をすると圧倒的大多数は「C」、すなわち3千円分のお食事券をもらう(実質利益は1,000円)を選択します。
しかし確率論での期待値は、
A・・・0円
B・・・(1万円×50%)+(▲2千円×50%)=+4,000円
C・・・▲2千円+3千円=+1,000円
ということでBの方がCよりも4倍もお得なんです。
不思議ですね?
■ 損失をしたくない理論、 行動経済学
スピードを競うゲームがあるとします。制限時間内にゴールに到達すれば賞金1万円。
そのコースの途中には扉があり、その扉を開けるかどうかはプレイヤー次第ですが若干時間がかかります。その扉を開けても十分制限時間内にゴールはできますがプレイヤーはそのことを知りません。
さて、その扉に以下のような2つの文章を貼ってABテストをしました
A.扉を開けると、開けない人より+100円お得
B.扉を開けないと、開ける人よりも▲100円の損
上記AとBは実は全く同じこと、つまり「しないとプラスマイナスゼロ、すると+100円」と言っています。
しかしAではゴールの時間が気になり扉を開けない人が多くなり、Bでは「損をしたくない」ということで開ける人の方が多くなります。
これも不思議ですね?
■ プロスペクト理論
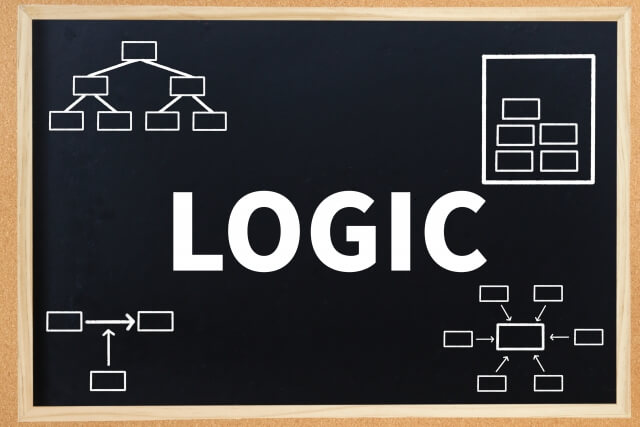
行動経済学に「プロスペクト理論」という考え方があります。
「~理論」というと小難しく感じますが、要は「~という考え方」という意味ですから安心してください。
プロスペクト理論とは、
・ヒトは得をすることよりも損失を避ける方を選ぶ習性がある(=損失回避性)
ことを述べた理論で、要は「損をしたくない!」という心理、行動のことです。
冒頭の問いにおいては、ちょっと考えれば期待値としてBが良いことを理屈ではわかります。
また2番目の例では「たった100円」という心理で「それよりもゴール」となりますが、そのたった100円でも「損をするんですよ」と言われればイヤなのでBが貼ってあると扉を開ける人が多くなります。
つまりヒトは利得の上乗せよりも損失の回避を優先する心理になるのです。
■ マーケティングへの活用
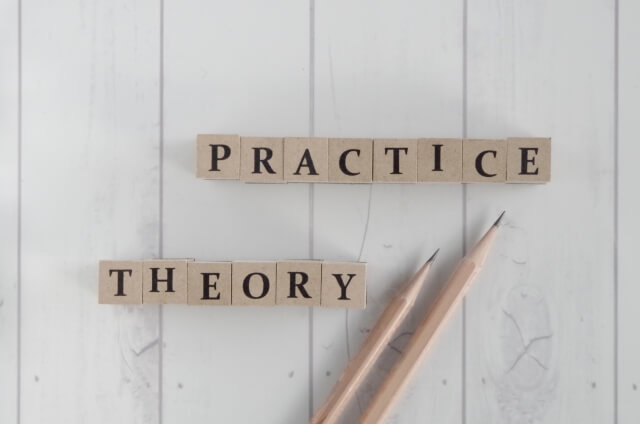
このことはマーケティングで大いに活用できます。
例えば欲しい商品があるとして、
A.本日のご購入なら通常よりも5,000円お得です!
B.明日になったら通常価格に戻り、+5,000円となります!
というコピー文ではBの方が「今買わなきゃ!」という心理が働くはずです。
・期間限定キャンペーン
・「今だけ」キャンペーン
なども同様ですね。
同じことを告知するにしても言い方(伝え方)ひとつでターゲットの行動を喚起させる力が違うことが分かります。
さてこの理論、行動特性をパチンコマーケティングに活用できないか?と考えます。
■ パチンコ店での応用

「出ます、出します、取らせます」、これは古き良き時代のパチンコ店新装開店でよく使われたコピー文です。新装開店初日は通常よりも出すので来ないと損をすると思わせています。
(「初日に来ると得をする」という捉え方でもやはり「期間限定」という今行かないと明日以降では損をする、となります)
一昔前のイベントも同様ですね。
要は「この日に来ないと損をする(他の日では、他のお店ではだめ)」という意識を持たせることが顧客の強い来店動機になるということです。
もちろん今こういったコピー文を使うことはできません。だからこそ「この日」という日にしっかりと出すことが求められます。直接的な訴求ができない現在は、この繰り返しが「この日」に対する顧客の来店動機を創り出すことになります。そして「この日に来なきゃ、損」という印象を植え付けるのです。
今、イベントをしても伸びないと嘆いているお店は、これまでにこれとはまったく逆のことを繰り返してはいなかったでしょうか。
もちろんイベント日の財源確保と称して平常を下げる営業をすることは本末転倒です。あくまでイベントは「イベント」なのでプラスアルファであるべきです。
■ もう一つの理論、「フレーミング効果」
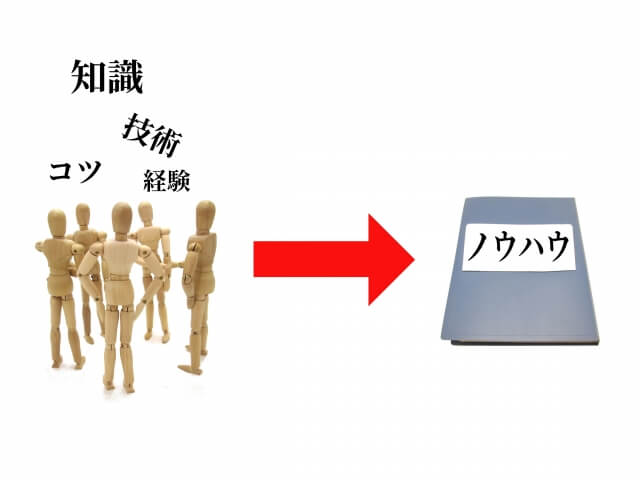
プロスペクト理論に似た理論に「フレーミング効果」というものがあります。まずは例を見てください。
いま、あなたはとある手術を受けるかの説明を受けています。
A.成功率は95%の手術です。
B.2,000回の実施例で、100回の失敗例がある手術です。
さて、どちらの説明なら受けようと思いますか?もちろんAだと思います。
しかしどちらも実は同じことを言っていますね。
フレーミング効果とは「受け手の印象を操作するために強調するポイントを変えた時の効果の違い」のことです。ヒトを動かせたいときはメリットを強調し、とどまらせたいときはデメリットを論点にすることでこちらの思うような行動に誘導することが可能なのです。
パチンコ店でのフレーミング効果の応用は、
A.確変継続率93%
B.確変中の確率1/2.06、4回転限定
で、どちらの方が「おっ?」と思うかです。もちろんこれはP大工の源さん超韋駄天のスペックで、どちらも同じことを言っていますね。
機種説明のPOP、イーゼルでの訴求はメリットとプラス面の訴求を意識することで印象が変わります。
■ プロスペクト理論とフレーミング効果

損失を回避したいという特性を「行動の選択」で考えたのがプロスペクト理論、「印象の操作」に応用したのがフレーミング効果、このように考えるとわかりやすいと思います。
「行動経済学」はこちらのページでも解説しています。
行動経済学という考え方(2017.11.20)
=======================
面白かった、と思った方はポチっとお願いします。
↓
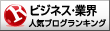
ビジネス・業界ランキング