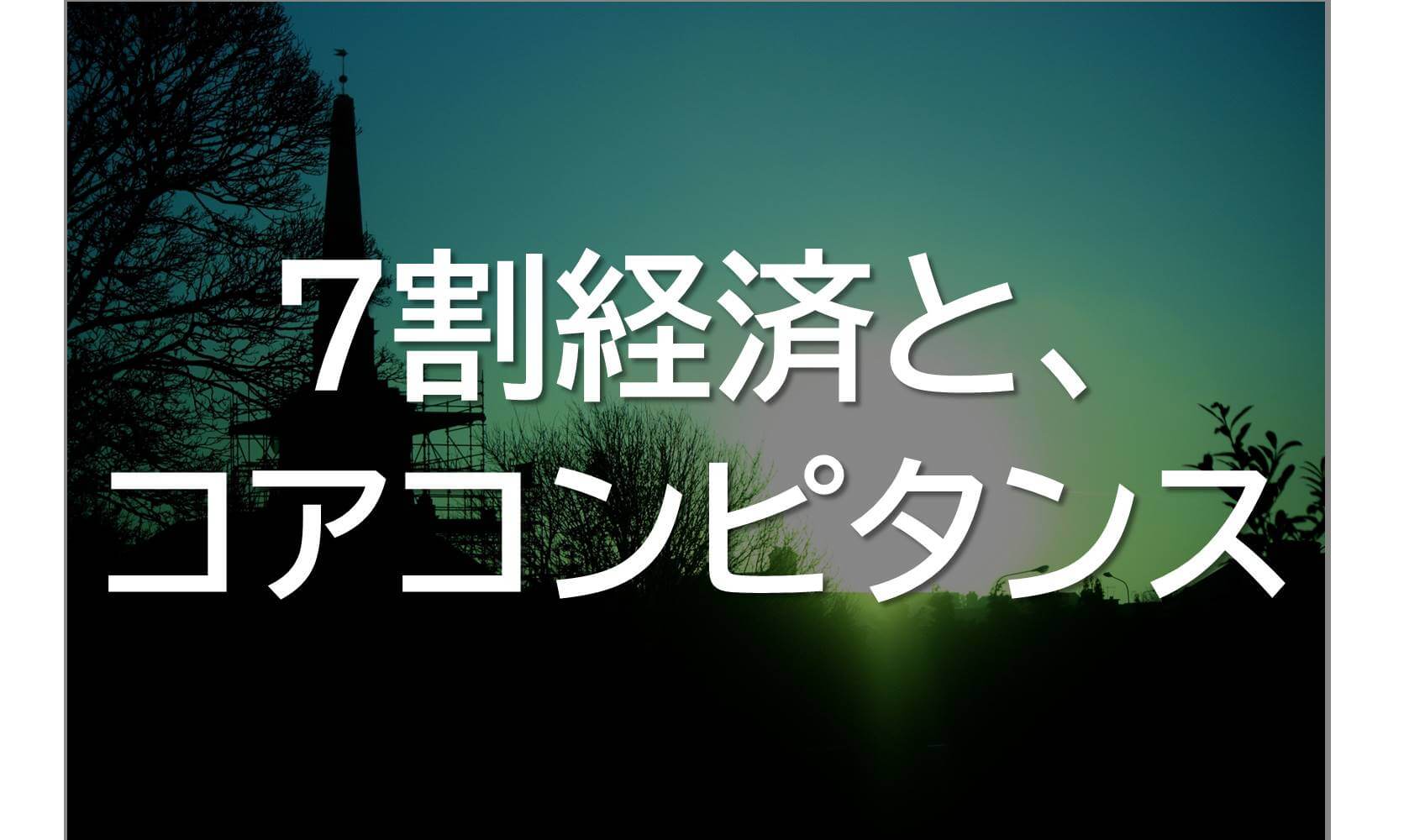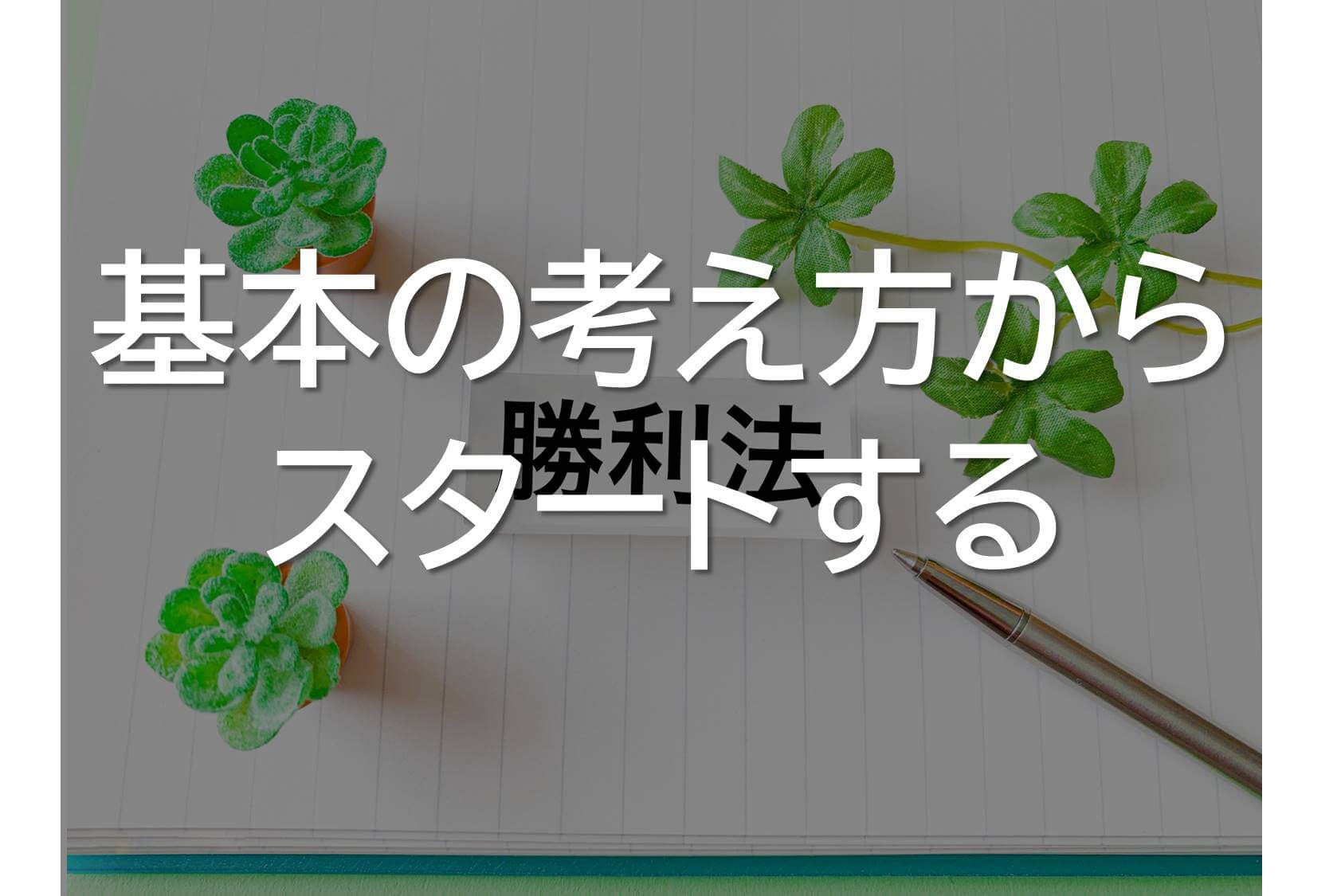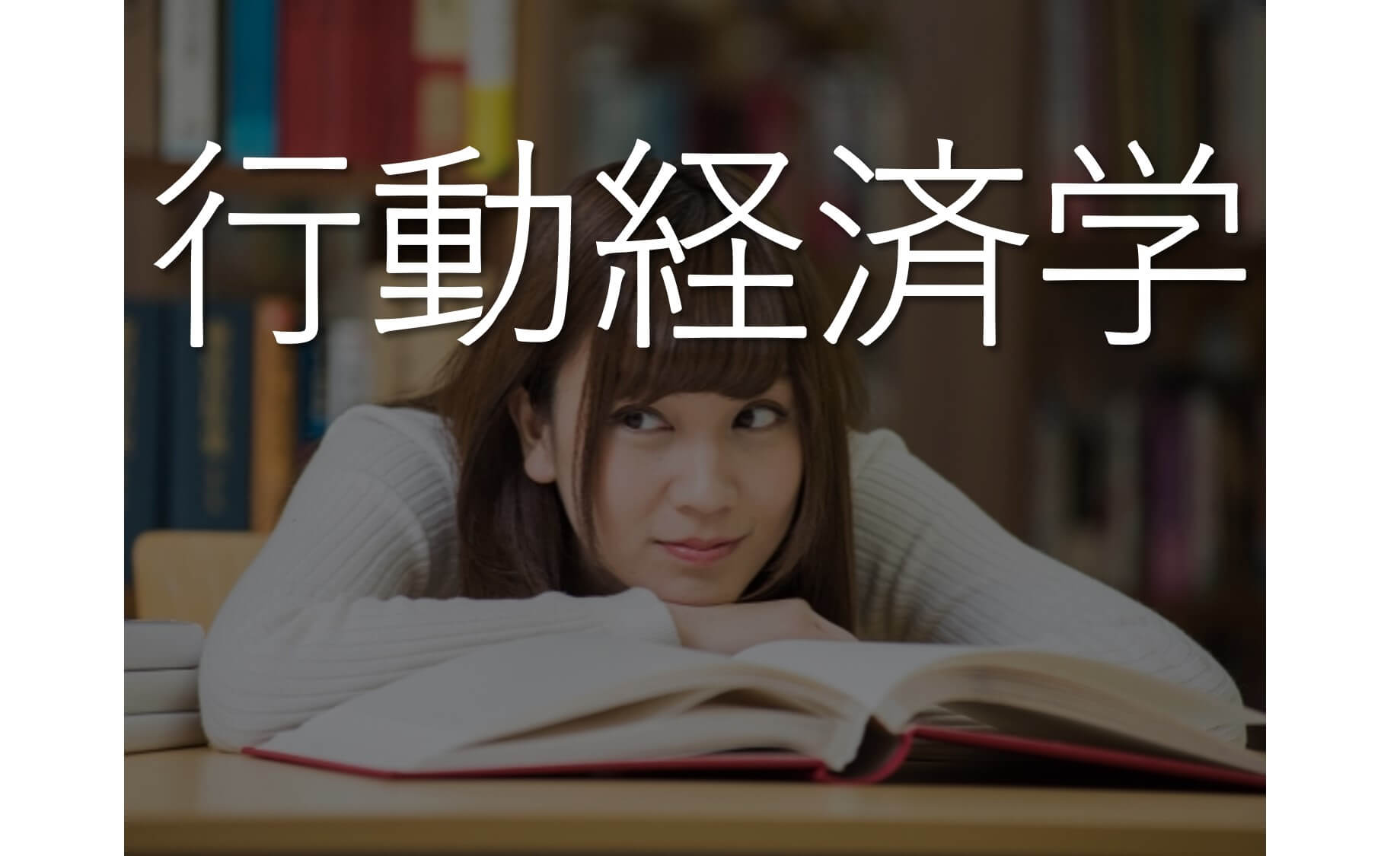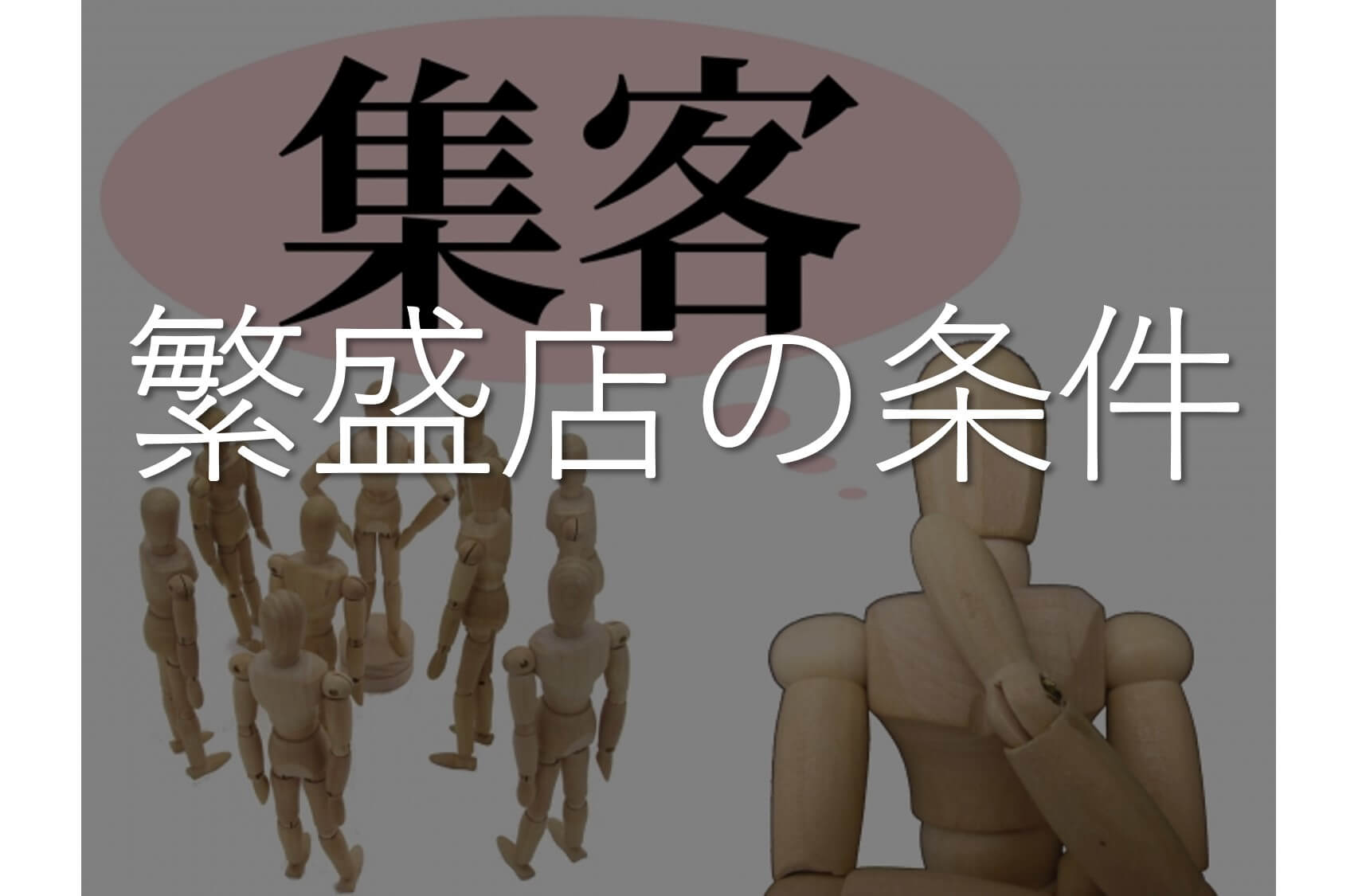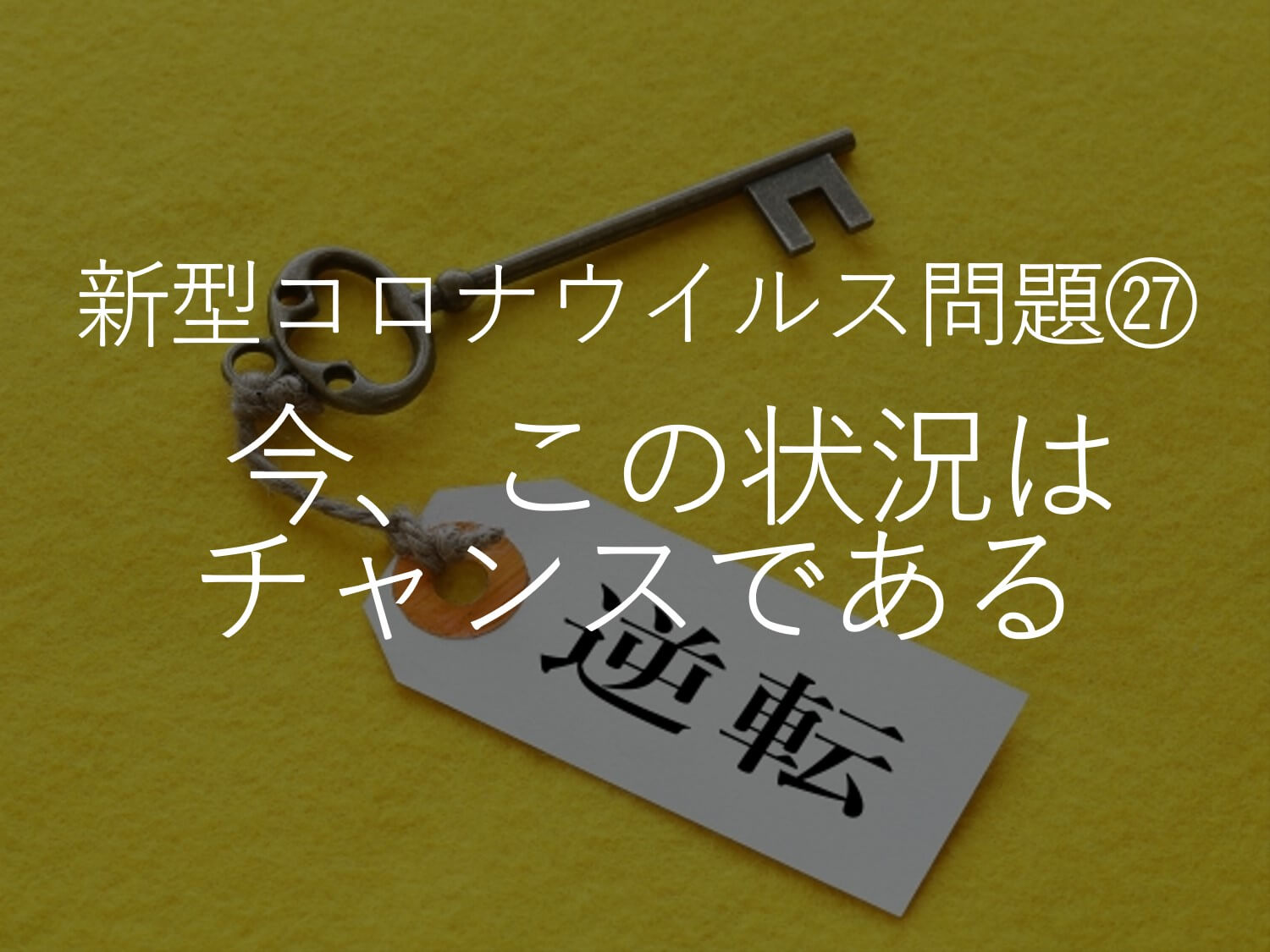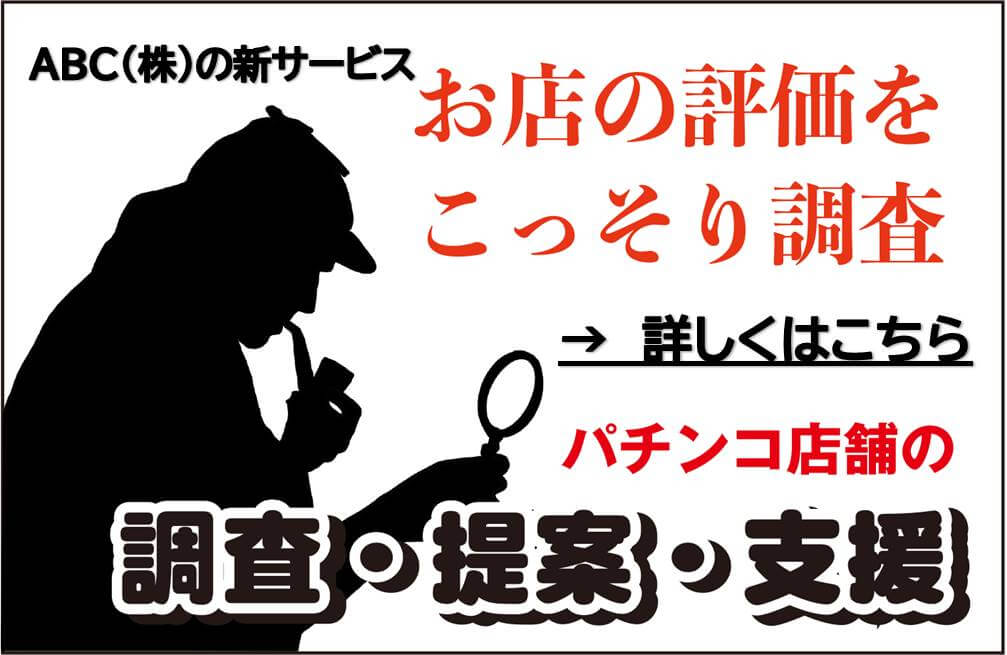私は大阪のある経営研究会に所属しています。
そこでは毎月3回ほどの小勉強会と月に1回著名な経営者を招いての講演会が開催されており、「企業とは、経営とは」という勉強をしています。
先日はある企業の経営者が「事後の百策よりも事前の一策」と題して、コアコンピタンス経営の重要さをお話してくださいました。
2時間という短い時間ながら非常に濃い内容で、今回はその内容のシェアをしたいと思います。
なお文中「経営者」と記載している部分は「リーダー」と置き換えて読み進めてください。(店長、マネージャー、主任等、誰しもがリーダー)
■ 事後の百策よりも事前の一策
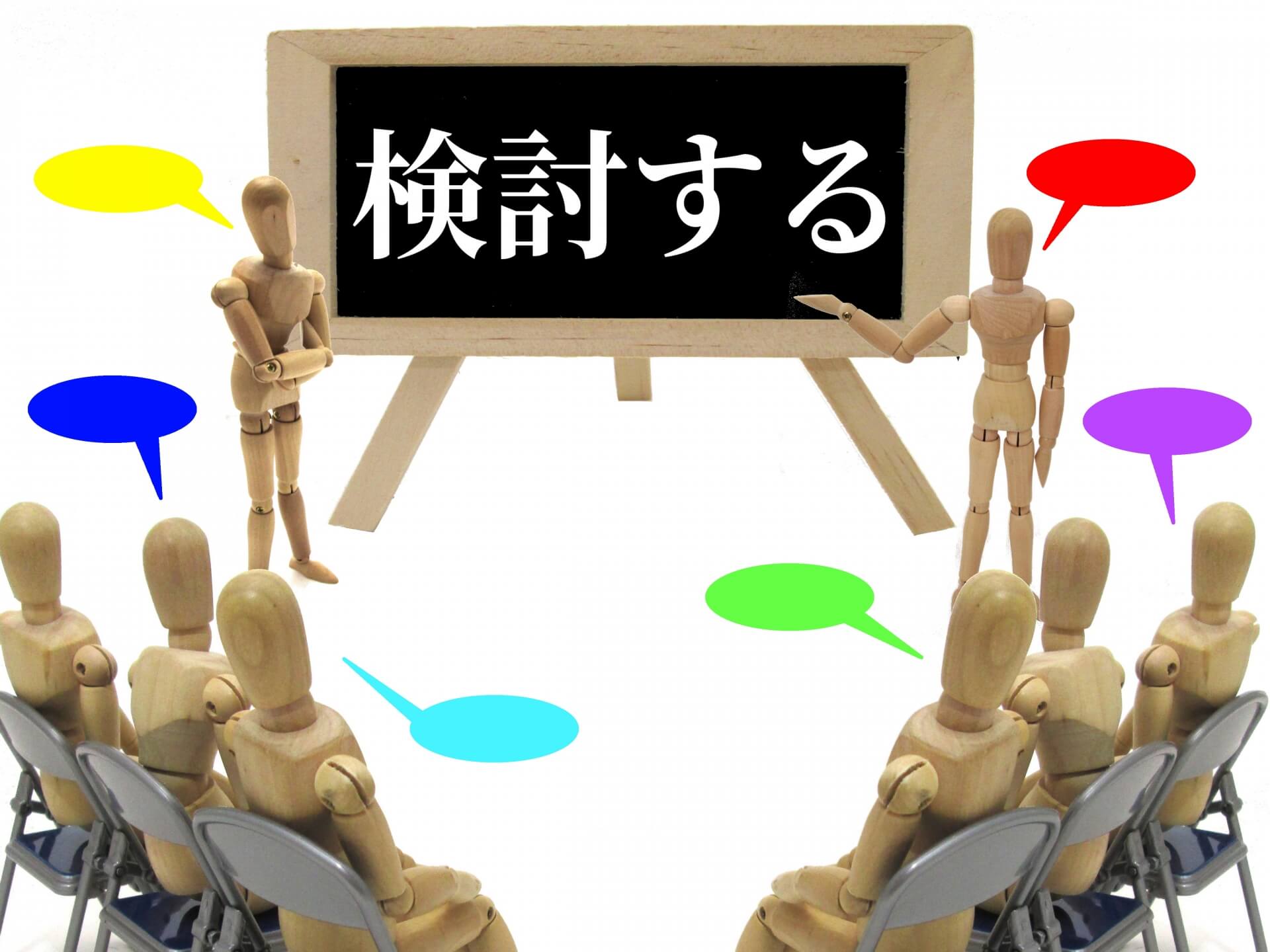
読んで字のごとく、です。「転ばぬ先の杖」と同義、何かの問題が起こった時に同じ結果(修正できた)が図れたとしても、事前ならちょっとの手間で済んだことが事後になるとかなり大変な苦労を伴います。
経営者は「最高の結果を求めて、最悪の状況を想定すべし」とされています。
「だろう経営」ではなく「かもしれない経営」をしなければいけないのです。
■ コアコンピタンス経営が重要

「企業の中核となる力」のことです。
自社が存続できている理由は何でしょうか?今、他社との競争力が低く後塵を拝しているとしても、そもそも存続できているのは何かしらの「根源的なパワー」があるからです。
その根源的、中核となるパワーは言い換えれば「強み」です。
この強みを認識し、もっと磨いていくことで現在の顧客との関係性を強固なものにすることが「コアコンピタンス経営」です。
今回の勉強会ではセブン銀行が一例として挙げられていました。
・セブンイレブンの強みはその店舗数とネットワークにあり
・銀行ATMの設置は顧客ニーズを掘り起こせる
・他行は自社でATMを設置するよりも低コストで利用者増を図れると考えるはず
・手数料に特化したビジネスモデルをつくる
これらの仮説を立て、数字からの実行可能性を検証し、そして成功に導いた、とされています。
■ 7割経済 というニューノーマル

消費者はコロナ禍において大きな行動制限を余儀なくされ、これまで当たり前だと思っていたことが当たり前でなかったことを知りました。
その中には「あれ?なくてもいいじゃん?」と気づいたこともあります。
「不要不急」を知った顧客、その先にあるのは7割経済=市場規模がコロナ禍前の70%になるという、ニューノーマル時代です。
これにより消費者は、
・これまで気にしなかった「不必要」を認識した
・本質的な価値を求める目が強くなった
・随意契約が成り立たず、比較するようになった。
となりました。
自社の提供する「価値」は顧客にとって必要なものか、不必要なのか?
自社の提供する「価値」は顧客が求めているものなのか?
自社の提供する「価値」は競合との比較優位にあるか?
経営学者で「競争の戦略」著者であるマイケル・ポーター博士は企業の「敵」を5つに分類しました。(ファイブ・フォース)
その「企業の敵」には「顧客」も含まれています。敵である顧客の攻略も企業がすべきことなのです。(ファイブ・フォースその他の4つは同一業界の競合、新規参入企業、仕入れ業者、代替品。)
7割経済=市場が70%に縮小するというのは自社だけの問題ではなく顧客の市場(や、財布)も同じです。ということは買い手も縮小するのですから、これまで何とかなってきたことがこれからはよりシビアな眼で見られることになります。
これからは本当の意味での「本物」だけに、生き残る資格があります。
■ 利益の源泉
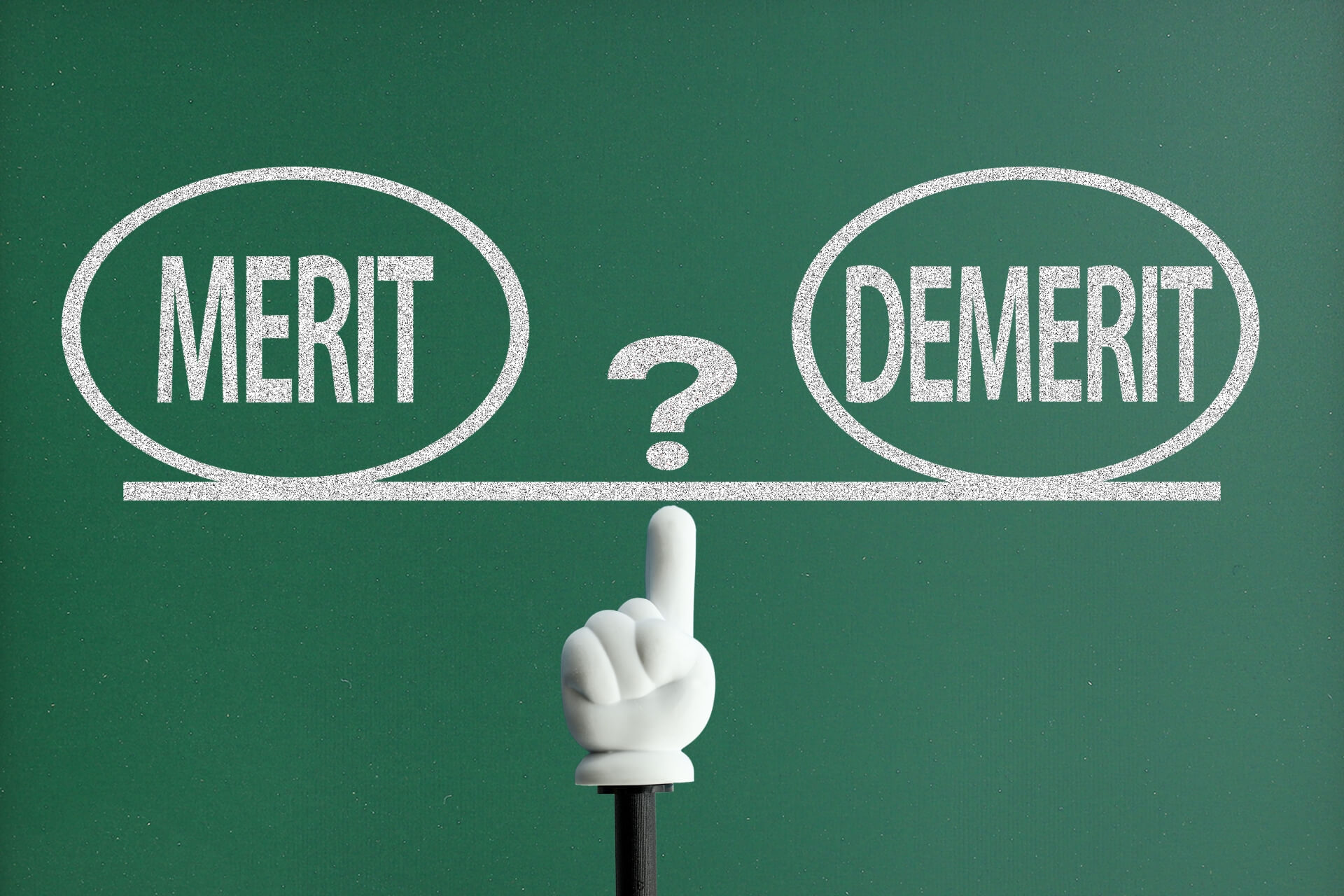
利益の源泉はどこにあるのかと聞かれれば、それは競合他社との違いであると言えます。
同じような商品でも選ばれるものと選ばれないものがあり、選ばれるから利益が生み出されます。選ばれなければ利益は生まれません。
競合が一切存在しない市場、商品ならばいいでしょう。
でも大多数はそうではなく、同じようなカテゴリーから「選ばれる」必要があります。
「このカテゴリーの商品を求める顧客はいる、しかし自社の商品とは限らない」のです。缶ビール市場を想像すればすぐに理解できますね。
■ 競争とは

「競争とは他社とのレースで先を行くことではなく、まったく違うルールで違うコースを走ることである」、マイケル・ポーター博士は競争をこのように定義しています。
他者と同質の戦いで精度を上げる、質を上げることを繰り返す先には高確率で低価格化での戦いに行きつきます。このような戦いは結局お互いに疲弊することにつながり馬鹿げています。
必要なのは勝負をしないこと。
マイケル・ポーター博士は、
「組織が競争に勝てるかどうかは、独自の価値を生み出せるかどうかにかかっている
「1位を目指すのではなくユニークになれ」
「競争の本質とは、競合他社を打ち負かすことではなく、価値を創造することにある。」
と言われました。
上記のことができないから価格競争が引き起こされるのです。
ライバルに勝つのではなく、顧客に勝つのです。
■ 満足の提供

競合他社を負かすことではなく顧客の満足を提供することに主眼を置いてください。
見るべきは自社でも競合でもなく、顧客なのです。
自社の利益=プロフィット
顧客の利益=ベネフィット
プロフィットの最大化を目指すのではなくベネフィットの最大化を目指すのです。
ベネフィットの最大化をするには差別化し、競争優位を作り出さないとならず、この源泉が「コアコンピタンス」となります。
■ まとめ
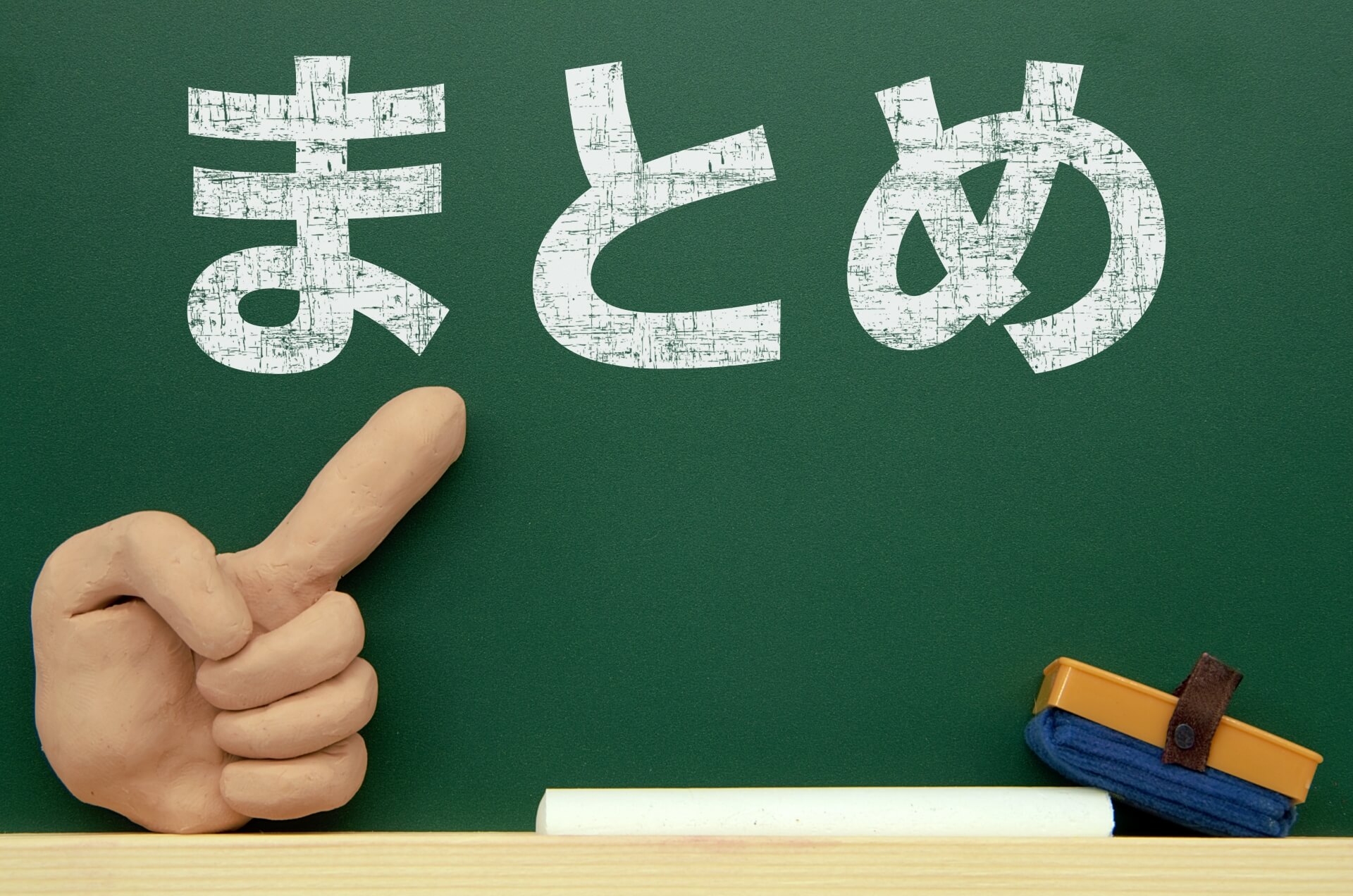
新型コロナウイルスは世界を一変させました。これはマイナスの面と同時にプラスの面も生じさせています。
プラスの面とは、
・自社の行動を見つめ直す機会を得られた
ことに尽きるでしょう。
もちろんこの「機会」は、それと気づかない人(企業)にとっては致命傷と捉えてしまったかもしれません。
しかし気づいた人(企業)にとっては「会心の一撃」につながる光に見えるはずです。
現状を嘆いていても何も生まれない、現状は事実として受け止めて「何をすべきか」を考え、行動に起こすことこそが求められます。
これまでなんとなくできていたこと、なんとなくしていたことが通用しない「新時代」だという認識で頑張っていきましょう。